介護職歴16年のべるべです。今回は施設や訪問介護の現場培った【認知症ケア】について発信します。下記のようなお悩みはありませんか?
今回の記事では介護職歴16年間で培ってきた3つの内容を紹介します。
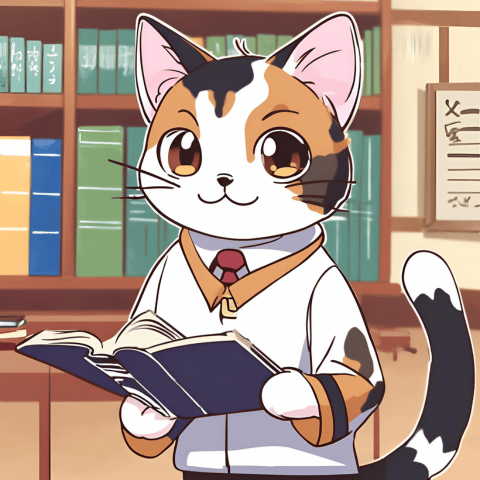
難しく考えず、シンプルに考えてみましょう!皆さんのお仕事のヒントになると、うれしいです。
未経験・初心者でもできる認知症ケア3つのコツ

認知症ケアには細かい工夫が必要だとか、経験と知識が絶対不可欠だと思っていませんか?確かに、その場その場の状況に応じて対応は異なため、工夫や経験はあれば尚良しです。ですが、それだけではありません。
私が16年間、施設や在宅で実際に働いた中で得た経験に基づく、認知症ケアのコツについてお伝えします。手前味噌で恐縮ですが、カイテクなどで色々な施設にいきますが、どこに行っても「声かけが上手だね!」と言われます。是非、参考にして下さい。
「え?そんな事?」と思うかも知れませんが、効果は抜群です!
詳細について説明します。
まずは名乗る所から始めて知ってもらう。
介護職の方は認知症の利用者さんの事を知ってます。逆に、認知症の方々は介護職の方々の事を覚えていないケースも多いです。
なぜ名乗るのか?
生活の中で介護を受ける際に下記のように感じている認知症の方も少なくないです。
もしみなさんが、”知らない人”から突然このような声をかけられたら、どう思うでしょうか?
「食事の時間です。」
「トイレにいきましょうか。」
「お薬です、飲みませんか?」
不安でしかありませんよね?
では今度は下記の状況であったらどうでしょうか?
「おはようございます、べるべです。食事の時間です。」
「こんにちは、べるべです。トイレに行っておきませんか?」
「こんばんは、べるべです。お薬です、飲みませんか?」
だいぶ印象が変わりませんか?
名前を名乗る事でまずは”知らない人”という障壁を乗り越えられます。
名乗っても意味がない?
上記のような声が聞こえそうですが、本当にそうでしょうか?
認知症があっても皆さんと同じ一人の人間です。名前も知らない人よりも名前を知っている人の方が少しでも安心感はありませんか?
【名乗るメリット】恐怖感が一旦減少する
名乗る事の目的は”少しでも不安感を軽減して安心してもらう事”です。
このような状態にいる認知症の方々に少しでも安心をしてもらえるよう配慮しましょう。
【名乗るメリット】コミュニケーションのキッカケになる
「誰ですか?」と聞かれたらチャンスです。相手はあなたの事を知ろうとしてくれています。”この人なら大丈夫だ!”となるような関係性を築く絶好の機会です。
上記3つの声かけや行動を起こして認知症の方々の不安を取り除けるよう支援しましょう。
【名乗るメリット】続けることで「聞いた事がある名前だ!」に変わる
毎日名乗り続ける事で認知症の方によっては名前を覚えてくださる事があります。こうなると強いです。
お知り合いの関係を築く事で関係性が深まります。様々な支援がスムーズにいきます。何より、あなた自身の働くモチベーションが上がるでしょう。
認知症の方の世界観に溶け込む
認知症の方々は様々な世界観の中にいます。
この世界観を受け入れ、認知症の方々の世界観に入れるように努めましょう。その世界観を一旦受け入れて、その世界観の登場人物の一人になるのです。
世界観に溶け込むには?
例えば、家事や子育てをしていた頃の世界観にいる認知症の方を例にします。
”食事の時間”という事を伝えたい場合
「〇〇さん子育てで忙しそうだから、私ごはん用意しました。今のうちに食事を済ませちゃってはどうですか?」
もし、泥棒に追いかけられて怖い思いをしている認知症の方がいれば
・「何を取られたんですか?一緒に探しましょう!」と声をかけたり
・忍び足で人がいるスペースに向かったり
・お巡りさんになりきってお話を聞いてあげたり
相手の世界観にお邪魔をしましょう。
その上で現実にこれから行う必要のある介助を行いましょう。
良く聞く【否定をせず受け止めましょう】という話です。
【世界観に溶け込むメリット】無理強いな支援にならない
世界観を知ろうという姿勢があるとおのずと「まずは相手が何を考えているのか?」というスタンスになります。
【世界観に溶け込むメリット】穏やかな生活に繋がる
自分の世界観が認められる事で認知症の方の精神的な安定になります。
【世界観に溶け込むメリット】本当に困っている事が何かわかる
一緒の世界観を見ることが出来ると本当の困り事が見えてきます。妄想や幻覚、不安といった心理症状、徘徊や不穏、介護への拒否といった行動症状。こういった周辺症状を見るのではなく困っている背景を知る事ができます。
どうしたら安心できるかは、利用者さんの世界観の中にヒントがあります。
認知症の方の声や表情に親身に向き合ってみると解決する事が多いです。
”笑顔”でコミュニケーションを図る
認知症ケアでは初回の声かけ時の第一印象が大事です。ここが抜けてしまっている人が多い印象です。日頃からバタバタと忙しなく走り回っていませんか?
笑顔で接する必要性
認知症があっても人です。支援者側の顔色や声のトーン、表情はわかります。
あなたの目の前に下記のような人がいたら、その人に話しかけたいですか?
認知症の方々の中には、言葉の理解が難しい方もいます。笑顔という非言語的コミュニケーションはとても重要です。介助技術はとっても上手でも笑顔でなくては、認知症の方々の不安感は払拭しきれません。
認知症の方々とコミュニケーションを図る上で大切なポイント3つを紹介します。
この3つのポイントについて詳しく解説します。
穏やかに笑顔で
認知症の方々の立場になって考えてみましょう。
あなたの前に知らない人間が近づいてきます。
無表情で、大きな声で「お手洗いいきましょうか。」と小走りで近づいてきました。
身構えてしまいますよね。
これが穏やかな雰囲気で笑顔であったらどうでしょうか?
認知症の方々は脳の障害により少し前の出来事を忘れてしまい、同じ事を繰り返し何度も聞いてくる事が少なくありません。
- 不安による影響から何度も同じ事を繰り返し聞いていたり
- 自分自身がおかれている状況が理解できず繰り返し聞いてきたり
- 純粋に記憶からスッポリと抜けてしまっている繰り返し聞いてきたり
繰り返し聞かれる事で支援者側が苛立ってしまう事もあります。しかし穏やかに笑顔で話を聞きましょう。上辺だけで聞くのではなく、何が原因で聞いているのか?出来るだけ穏やかな気持ちで話を聞きましょう。
2、3分でも一緒に腰掛けて話を聞くだけで認知症の方々が安心する事も多々あります。
声の大きさ、声のトーン
支援者側が大きな声で話かけると意図せず下記3つのように認知症の方々に受け捉えられてしまいます。
声のトーンで気にかけるコツは下記3つです
認知症という病だけでなく、難聴など併せ持っている方もおり様々なケースがありますが”しっかり相手に伝える”という意識が必要です。
相手に伝わりやすい言葉を選んで使う事も重要です。
目線をあわせる
目線をあわせる時のポイントは3つです。
言葉や表情を使わずとも、目線をあわせるという行為だけでも相手に多くの安心感を伝える事ができます。
いくら献身的な支援でも笑顔と安心感を感じる事ができない支援では、認知症の方々からは受け入れてもらう事は難しいです。
あなたは大丈夫?やってはいけないNG支援

ここからは避けるべきNG支援について紹介します。
否定する
説明する必要もない程、定番なNG例です。
前述の世界に認知症の方々はいます。「食事はさっき食べた」「泥棒はいない」というような声かけ程、無駄なものはありません。
ごまかす
不安や混乱がある認知症の方に対して曖昧な表現でごまかしたり、適当にあしらう事はNGです。認知症の方々でも忘れずに覚えている事も少なからずあります。
曖昧な表現や適当な対応によって起こり得るトラブルもあります。
こうした場合もちろん「聞いていた話と違う」や「うそをつかれた」と受け止められます。その後の関係性にヒビが入り、より支援が難しくなります。
出来なかった事を怒る、指摘する
こんな声かけはもちろんNGです。
認知症の方々だって人間です。プライドや怒られてしまう事で羞恥心や劣等感を感じてしまいます。出来る能力だって奪ってしまう可能性もあります。
支援者側が落ち着き、認知症の方がどのような気持ちだったか推測してあげましょう。
認知症ケアを学ぶメリット
認知症ケアが上手にできると、下記3つのメリットが生まれます。
仕事の満足度が向上する
認知症の方々も支援者側もお互いが気持ち良く過ごせる事で、お互いに満足度が向上します。
認知症の方々から見ると
支援者側からみると
スムーズに仕事が行く事で焦りがなくなります。焦りがない状態であれば、心に余裕が生まれ創意工夫されたコミュニケーションが図れます。
心理的な負担の減少・軽減が図れる。
認知症の方々も支援者側もお互いに負担が減ります。
認知症の方々からみると
支援者側からみると
介護での精神的・心理的なストレスが減ります。あなた自身のプライベートも充実してきます。
あなたの評価が上がる。
みんながWIN-WINな関係になります。
まとめ
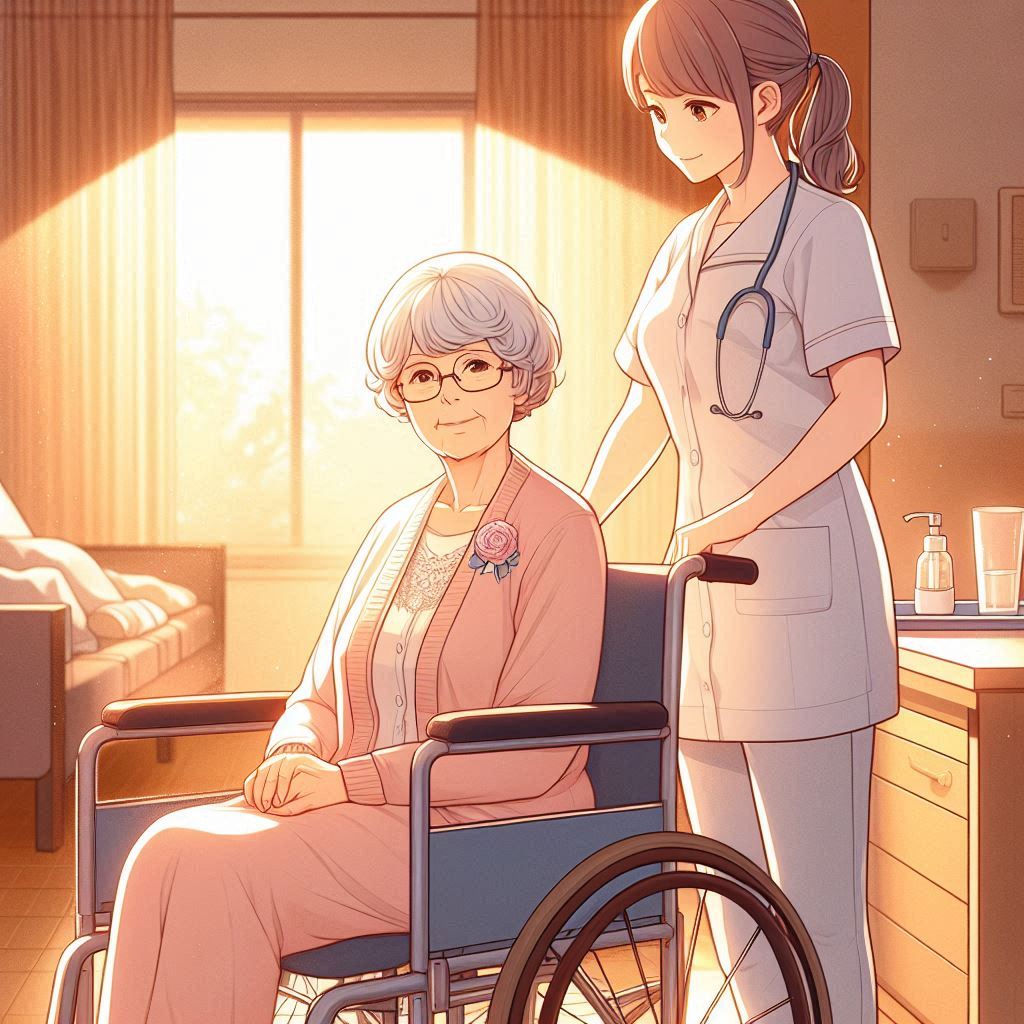
利用者さんの認知症の分類や程度によっても状況は様々だと思います。しっかり覚えている事と忘れてしまっている事がマダラな認知症の方もいらっしゃいます。
認知症があっても一人の人間です。不安や混乱、恐怖におかれている認知症の方々の声をまずは聞く事から始まります。
認知症の方から「あなたで良かった。」と言われるようになると喜ばしいですね。
もし認知症ケアでお困りであれば是非、実践してみてください。みなさんの参考になれば幸いです。
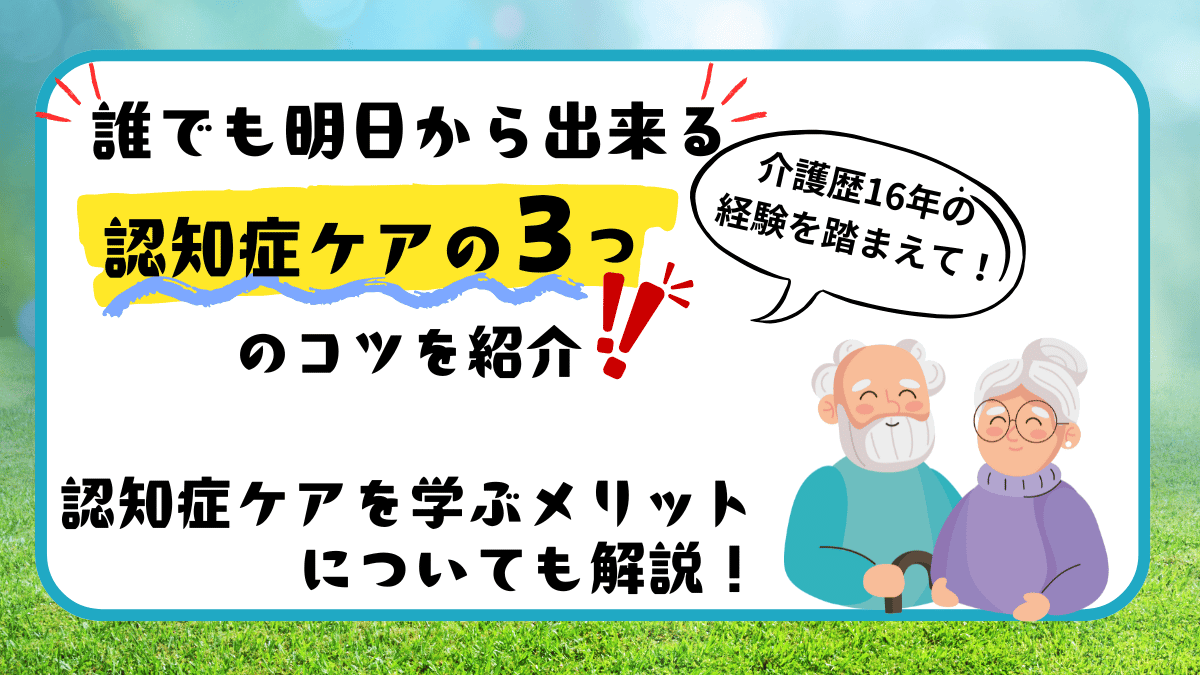


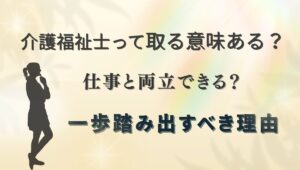
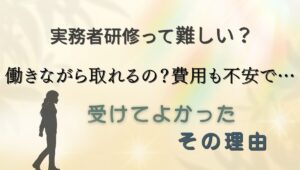
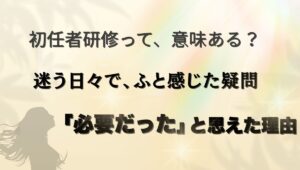
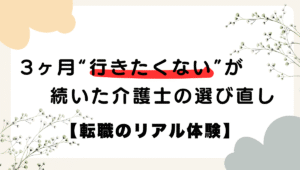
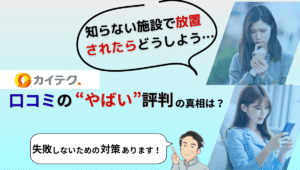
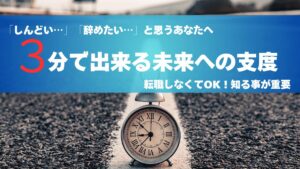
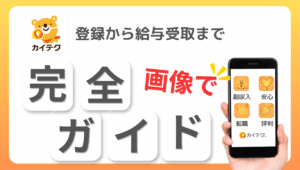
コメント