無資格のまま、介護の現場で働いている。
そんな日々の中で、ふと思うことはありませんか?
利用者さんの名前は覚えた。移乗も少し慣れてきた。でも、ふと不安になる瞬間はありませんか?
- 上司からの評価が伸びない。
- 責任ある仕事を任せてもらえない。
- 昇給・昇進の話になると、いつも「資格を持っている人」が優先される。
こんな不安を、ずっと感じたままで働き続けますか?それとも、何かを変える一歩を踏み出しますか?
私は現場で働き、そして転職エージェントとして、多くの介護職の方と関わってきました。
その中で強く感じたのは、「資格がすべてじゃない。でも、資格があると“変わるもの”も確かにある」ということでした。
この記事を最後まで読むことで、「このままでいいのか?」という不安に答えが出ます。
- 無資格のまま働き続けると、何が起きるのか
- 資格を取ることで、どう未来が変わるのか
- 現場で“評価される人”と“埋もれていく人”の決定的な違い
- そして、自分はどちら側に立つのか
立ち止まるか、動き出すか。選ぶのは、あなたです。
▼共感した方はこちらもぜひ
【転職のリアル】3ヶ月「行きたくない」が続いた私が、転職して気づいたこと
「このままでいいのかな?」そんな日々を過ごしていた私のリアル体験談です。
“無資格でもできる”けど、“無資格のままでいい?”とは限らない
無資格で働き続けることで、どんな現実や壁に直面するのかを率直にお伝えします。
「無資格でも働ける」
たしかに、それは事実です。
実際、現場では無資格でスタートした人が多く、今も戦力として活躍している人はたくさんいます。
でも一方で、こんな声を聞いたことはありませんか?
これが、“無資格のまま”で働き続けた先に見えてくる限界です。
介護の仕事は、知識や資格だけでは測れない“人としての関わり”が大切。
それは間違いありません。
でも現実には、資格を持っている人の方が優遇される構造にあります。
・評価されやすく
・昇給や昇進のチャンスも多く
・自分の意見が通りやすくなる
「資格がない=できない」ではありません。
ただし、「資格がない=選ばれない」ことは確実です。
だからこそ、今の自分に問いかけてみてください。
少しでも「不安」や「違和感」を感じたなら、この記事を読んでいくことで、次の一歩が見えてくるはずです。
現場で感じた“資格のある人・ない人”のリアルな違い
「資格がある・ない」で、現場でどう見られ、どう違ってくるのか?そのリアルをお話しします。

「資格がある人が優れていて、ない人は劣っている」という事?
そんな単純な話ではありません。
実際、こんな現場の声を私は何度も聞いてきました。
初任者研修だけの方でも、利用者さんに寄り添う姿勢や気配りが素晴らしく、チームからも厚く信頼されているケース
介護福祉士の肩書きを持ちながらも、基本的なケアが雑になってしまうケース

「でも、“資格がある”って、それだけで“判断できる人”になれるわけじゃないけど、判断の“根拠”は確実に増えるんだ。」
迷ったとき、行動の裏にある理由を説明できる。
あの人がなぜああ動いたのか、自分ならどうするかを考えられる。その力を、資格を通じて手に入れている人は多いです。
無資格のままだと、不安を抱えたまま動くことも多くなります。
- 「これで合ってるのかな?」
- 「どうすればいいの?」
でもそれは、やる気やセンスがないわけじゃない。知識の“土台”がまだ整っていないだけなんです。
資格は、現場で即使える武器ではないかもしれません。
でも、経験を“意味あるもの”に変えていく道しるべにはなります。
これまでの経験がつながる。その感覚を持てることこそ、資格の大きな価値です。
今までの経験が“つながる感覚”を得られるのも、資格を通じて得られる大きな価値のひとつだと思います。
資格は「道しるべ」、でも「お守り」じゃない
資格は魔法の道具ではないけれど、“判断力と信頼”を育てる土台になります。
介護の資格を取れば、不安がすべて解消される。
そんなふうに思っている方も、もしかしたらいるかもしれません。
でも、正直なところ、資格を取っても不安がなくなるわけではありません。

「資格があるからって、全部に自信が持てるわけじゃない。
でも“判断の根拠”は確実に増える。それは間違いない!
学んだ知識と、実際の現場には“ズレ”があります。
机の上で覚えた手順や考え方が、そのまま現場で活かせるとは限りません。
【POINT】
資格で得た知識は「応用のための土台」になります。
現場で直面した場面に対して思い出せる、考えられる“引き出し”が増えるのです。
- 「これって授業でやったあの内容に近いかも」
- 「この対応、たしかテキストで見たケースに似てるな」
そしてもうひとつ。
資格を持っていると、自分自身の判断に対する「根拠」が生まれます。
たとえば、誰かに質問されたときに、
「これはこういう理由があってこの対応をしています」と説明できると、周囲からの信頼にもつながりますし、自分の中でも迷いが減っていきます。
資格は、介護の現場で迷ったときに道を照らしてくれる“地図”のような存在。
でも、“お守り”のように持っているだけで自分を守ってくれるものではありません。
大切なのは、資格を活かせる力を少しずつ育てていくこと。
その一歩として、資格の取得を考えてみても良いかもしれません。
今は原則必須|まずは「認知症介護基礎研修」から
「資格がなくても働けます」
そう言われて、介護業界に興味を持ち始めたあなた。
でも、実は2024年度から、無資格のまま現場に入る場合は『認知症介護基礎研修』の受講が原則必須になりました。
つまりこれは、“介護業界で働く最初の入場チケット”です。
言い換えれば、介護の仕事に挑戦する人すべてが通る“最初の関門”なのです。
受講は各都道府県の指定窓口からスタート

「どこで申し込めばいいの?」
戸惑う人も多いはず。
この研修は、全国の自治体がそれぞれ運営しており、申し込み方法や受講形式も地域によって少しずつ違います。
まずは「(お住まいの地域名)+認知症介護基礎研修」で検索してみましょう。
都道府県または市区町村の福祉関連ページに、受講案内が掲載されています。
申し込みは基本的に“職場を通じて”
この研修は、まだ介護現場で働いていない方が直接申し込めるケースもあります。

しかし、多くの自治体では「就職後に事業所から申し込む」スタイルが基本です。
つまり、未経験OKの職場に採用されたあと、会社を通じて研修を受ける流れ。
就職前に不安な人は、事前に「この研修は受けられるか」確認しておくと安心です。
スマホ・PCで受講OK。オンラインで完結する自治体が多数
受講形式は、ほとんどの自治体でeラーニング(オンライン動画視聴)が主流です。
ただし、少ないですが一部の自治体では対面形式で実施している所もあります。
スマホやPCで視聴できるので、自宅でもスキマ時間でも学べます。
「忙しくて通えない…」という人でも、無理なく受講できる仕組みになっています。
オンライン受講であれば3〜4時間、分割視聴できる自治体も
「まとまった時間なんて取れない…」と心配になりますよね。
受講形式は2パターンあります。
- オンライン受講(eラーニング)
- 対面での受講
オンラインの場合、動画の総視聴時間は約2.5〜3時間程度。
一部の自治体では、ログインし直せば続きを視聴できる「分割受講」にも対応していますが、自治体によって仕様が異なるため、事前に自治体の研修ページで詳細をチェックしておきましょう!
少ないですが、一部の自治体では対面研修を行っており、その場合は6時間程度のカリキュラムになることもあります。対面の場合、休憩時間やグループワーク、質疑応答などが含まれているため、時間が少々長くなっています。
とはいえ、講師とのやり取りや質問ができるので、学びの深さで言えばこちらも魅力です。
「何日もかかるんじゃ…」と構えていた方も、これなら取り組みやすいはず。
修了証は、あなたの“学びの証”になります
受講を終えると、自治体から修了証(PDFまたは書面)が発行されます。
これは、今後の就職活動や転職活動でも「受講済みの証明」として使えます。
研修を終えると、修了証(PDFまたは書面)が発行されます。
これがあると“介護の学びを始めた証”として信頼感につながります。
自分の成長を示すアイテムとしても大切な一歩です。
受講費用は無料 or 事業所負担。自己負担はほぼなし
「やってみたいけど、お金かかるのでは…」と不安な方も多いはず。
「受けたいけどお金がかかるのでは…」と不安になる方もいるかもしれません。
実は、多くの人が「無料」または「就職先負担」で受講できています。
まずは勤務先や地域の制度を確認してみましょう。
まずは“介護の入り口”として、この一歩を踏み出そう
この研修は、介護のすべてを教えてくれるわけではありません。
でも、「認知症の方とどう向き合うか」「どう関わるか」の考え方の基本が詰まっています。
知症の方との向き合い方や、介護の考え方の基本がわかる研修です。
この一歩を踏み出すことで、あなたの“支援者”としての道が始まります。
▼あわせて読みたい
【未経験OK最初に選ぶなら?介護職おすすめ職場タイプを比較!
資格だけじゃない。「働き方」にも目を向けて、自分に合った職場を見つけましょう。
資格を取ることで得られるものは、知識や評価だけではありません。
これからのキャリアの選択肢そのものが、大きく広がっていくのです。
あなたがこの先も“無資格のまま”でいるとしたら、3年後、どんな仕事をしているでしょうか?
資格だけでなく、“働く環境”もあなたの成長を左右します。
初めての職場選びで迷っている方はコチラもチェック!
未経験OK!介護職おすすめ職場タイプを比較する!
ステップアップするなら?資格ごとのリアルと選び方
「どれを取ればいいの?」「順番は?」に答える、リアルな資格選びの話です。

「いきなり介護福祉士を目指すなんて無理…。」

「資格を取るって、正直ハードル高そう…。」
そんなふうに感じているあなたへ。“焦らなくて大丈夫”という視点で、次の一歩を整理してみました。
無資格で働きながら迷っている方は少なくありません。
- 「このまま無資格で働き続けていいのかな…とモヤモヤする」
- 「どこかで資格を取った方がいいのかも…と思いながら時間だけが過ぎていく」
ここでは、介護職で多くの人が通る資格ステップを紹介しながら、それぞれあなたに合った資格が、きっと見つかります。
介護職員初任者研修(旧:ヘルパー2級)

「介護の仕事に挑戦してみたいけど、何から始めればいいんだろう?」
そんな方にとって、最初の一歩となるのが「介護職員初任者研修」です。
この資格は現場に出てすぐに活かせる内容が詰まっています。
・身体介助の基本が身につく:食事・排泄・入浴など、日常生活を支える介助技術を学びます
・利用者さんとの関わり方がわかる:声かけや接し方の工夫など、コミュニケーションの基本を学びます
・認知症や高齢者心理の基礎理解:困惑せず対応するための知識と心構えが身につきます
座学+実技演習があり、修了時には修了試験もありますが、試験はきちんと受講すれば問題なくクリアできる内容になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受講期間 | 約1〜2ヶ月(通学+自宅学習) |
| 費用の目安 | 5万〜10万円前後(自治体や施設によって補助あり) |
| 学び方 | 通学制・通信制どちらも対応。働きながらの受講も可能 |
| 取得の難易度 | 修了試験あり。授業をきちんと受ければ、ほとんどの人が合格できる内容です |
実務者研修
次のステップとなるのが「実務者研修」。
これは介護福祉士の受験に必要な資格でもあり、たん吸引や経管栄養といった医療的ケアの基礎も学べる内容です。
介護職として、より専門的な知識と技術を身につけたい人に向けた一歩です。
この資格では、現場で“ワンランク上”の対応が求められる場面に備える学びができます。
・医療的ケア(たん吸引・経管栄養など)に関する知識と基本技術
・サービス提供責任者としての役割や記録の書き方
・認知症ケアや家族支援の考え方など、より深い理解が求められる内容
学び方は、通信+一部通学が主流。
働きながらでも無理なく学べる設計になっており、レポート提出や演習もありますが、計画的に取り組めば問題なく修了できます。
将来的にキャリアアップを視野に入れるなら、早い段階で取得を検討しておきたい資格のひとつ。
現場でより専門性の高いケアが求められる場面や、サービス提供責任者を目指す場合には、実務者研修が確かな土台になります。
受講期間は6ヶ月ほど。
費用は10万〜15万円程度とやや高めですが、こちらも補助制度の対象になることが多いです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受講期間 | 約6ヶ月(通信+スクーリング) |
| 費用の目安 | 10万〜15万円前後(補助制度あり) |
| 学び方 | 通信制+一部スクーリング。働きながらの受講も可能 |
| 取得の難易度 | レポート提出や実技演習あり。計画的に取り組めば問題なく修了可能 |
介護福祉士
介護職の国家資格である「介護福祉士」は、キャリアアップや待遇改善に直結する、いわば“プロフェッショナルの証”ともいえる資格です。

「そこまで目指すのはまだ早いかも…」と感じるかもしれませんが、この資格を持っているかどうかで、広がる未来の選択肢は大きく変わります。
この資格を取得する事で下記のメリットが得られます。
・介護の基本から応用までを体系的に整理しなおすことができる
・チームアプローチや倫理的判断など、現場での“質”を高める知識も習得可能
・資格取得後は、リーダー・管理職・研修担当など、任されるポジションも増える
・年収アップや待遇改善に直結しやすい(法人によっては資格手当+月2〜3万円の差がつくことも)
試験内容も幅広いですが、日頃の実務経験を活かして対策すれば十分に合格を狙えます。
合格率は約70%前後と比較的高く、働きながら目指す方も多いのが特徴です。
職場での信頼や評価を高めたい方、将来的にケアマネージャーなどを目指す方には、大きな一歩になる資格です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験資格 | 実務経験3年以上 + 実務者研修の修了 |
| 試験日 | 例年1月下旬(筆記試験) |
| 費用の目安 | 受験料約19,000円(別途テキスト代など) |
| 取得の難易度 | 合格率は約70%。経験を積んでいれば十分合格を目指せる |
比べてみてどうでしたか?
どれも一気に目指さなくて大丈夫。あなたの状況に合ったペースで、ゆっくり進めばOKです。
もちろん資格だけでなく、職場選びもあなたの未来を左右します。「どんな職場が合うんだろう…」と迷ったら、こちらもコチラ参考に!
現役介護士のリアルな転職体験談
自分にあったステップを選ぼう
「資格はたくさんあるけど、どこから始めるべきか迷っている…」
そんな方のために、主要な資格の試験概要を一覧にまとめました。
| 資格名 | 試験形式 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 介護職員初任者研修 | 修了試験(筆記/選択式) | カリキュラム全体の復習問題(講義や演習から出題) |
| 実務者研修 | レポート提出+実技演習 | 通信課題の内容、たん吸引・経管栄養に関する基本知識・技術など |
| 介護福祉士 | 筆記試験(マークシート式) | 13科目群から125問出題(2時間40分) ※人間と社会・介護の基本・医療的ケアなど幅広く出題 |
※初任者・実務者は「修了すれば取得」、介護福祉士は「国家試験合格で取得」です。
※「修了試験」とは、研修や講座を終えるための確認テストのことです。研修を受講し、試験に合格すると「修了証」が発行されます。
※「筆記試験」は国家資格取得のための正式な試験で、合格しないと資格を取得することはできません。
それぞれのステップを比較しながら、自分に合ったタイミングとペースで進めていきましょう。
「資格より人柄」は正しい。でも、資格が“ないと伝わらない”こともある
どんなに資格があっても、介護の本質は“人との向き合い方”にあります。
介護の仕事において、資格はたしかに大きな力になります。
しかし、資格が「人としての価値」や「介護職としての質」を決めるものではありません。
現場では“初任者研修だけ”の方が、介護福祉士よりも丁寧で素敵なケアをしているというケースは良くあります。
- 利用者さんに寄り添う姿勢
- 細かな変化に気づける感性
- 周囲とのチームワークの尊重

“人としての関わり方”は、資格の有無とは関係がないことが多いのです。
資格を持っているから偉い、持っていないからダメ。そんな世界ではありません。
ただし、ここでひとつ加えておきたいのが、
資格を持っているからこそ、自分の想いを“カタチ”にしやすくなるということです。
「こうしてあげたい」
「こう関わるのが良いと思う」
という気持ちがあっても、根拠がなければ説明ができません。
信頼されづらく、現場での発信力にもつながりにくいこともあります。
しかし、資格を通して学んだことがあると、“考えを言葉にできる・伝えられる”ようになります。
より良いケアにも、職場での評価にもつながっていきます。
だからこそ、気持ちがある人にこそ、資格という“言葉にできる力”を手にしてほしいのです。
介護は、結局は人と人との仕事。
必要なのは、資格ではなく“向き合う姿勢”です。その姿勢をしっかり伝えていくためには、資格が背中を押してくれる場面もあります。
だから、どちらも大事。バランスを取りながら、自分らしいケアを育てていけたら素敵だと思います。

資格は“評価の証”であり、“伝える力”の土台になります。
▼資格を取ったら、次は“自分に合う働き方”を
登録だけでも大丈夫?介護転職エージェントの不安と賢い活用術
資格を武器に「自分らしく働く」ために、転職エージェントを上手に使うコツをまとめました。
まとめ|資格は「現場で戦う道具」。主役は、あなた自身
介護の仕事は、資格がなくても始められます。
実際、無資格で素晴らしいケアをしている方もたくさんいます。
しかし、もしも
「このままでいいのかな」
「もっとできることを増やしたい」
上記のように悩んでいるなら“学びの準備が整ったサイン”です。
資格は、あなたの介護を支える“道具”です。
判断の軸となり、想いを言葉にし、ケアの意味を深めてくれる。
そして何より、自分らしい働き方や選択肢を広げるきっかけにもなります。
焦らなくて大丈夫。
でも、もし「やってみようかな」と思えた今が、ベストなタイミングかもしれません。
資格がすべてではないけれど、
資格があるからこそ見えてくる景色があるのも、また事実です。
だからこそ、
これまでの現場経験に少しの学びを重ねて、
“あなたらしいキャリア”と“あなたにしかできないケア”を、これから築いていきましょう。
資格を取ったあとは、“自分らしい働き方”を見つける事が重要です。
資格だけで終わらせない、“働き方”の見つけ方とは?
介護転職エージェントの上手な活用術はこちら
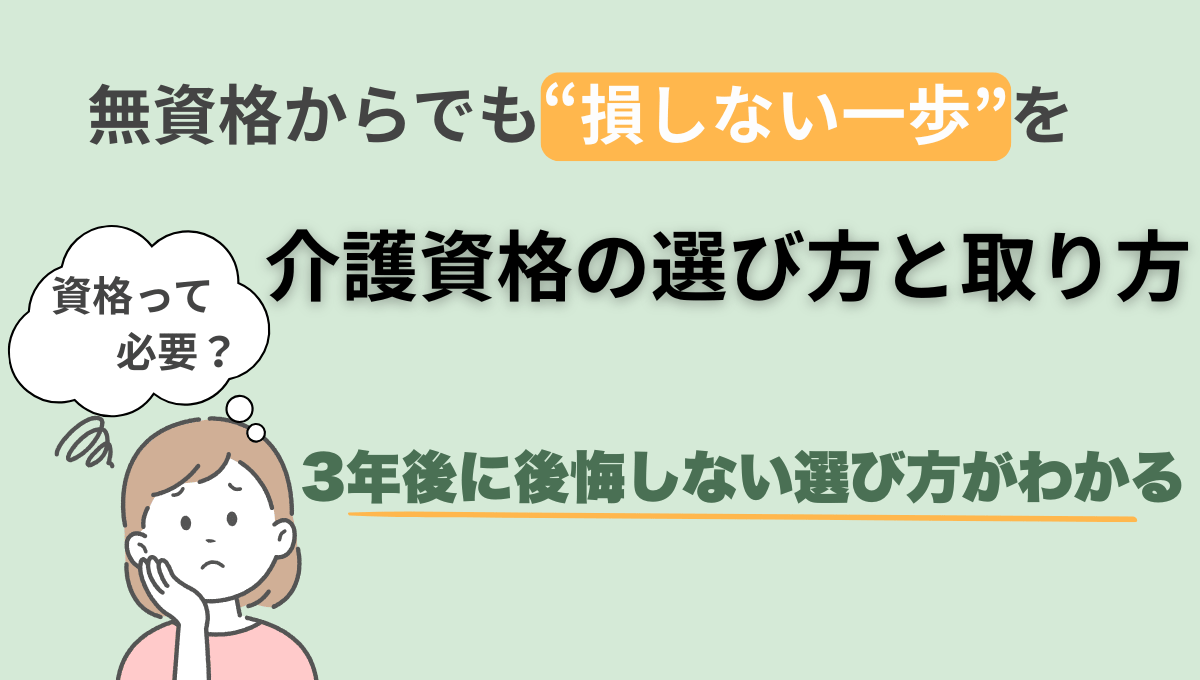

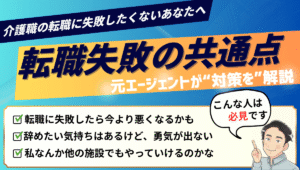
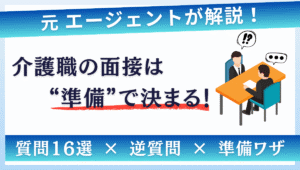
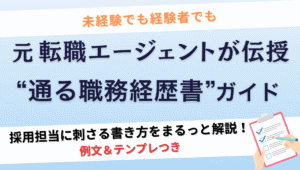
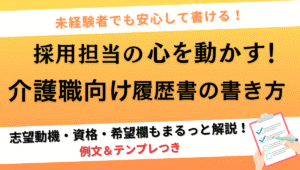
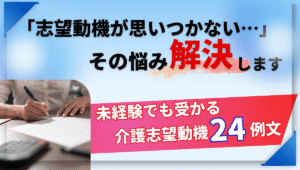
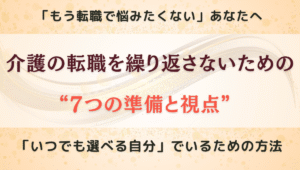
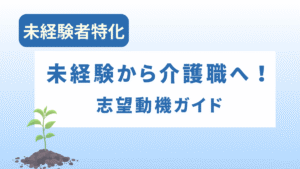
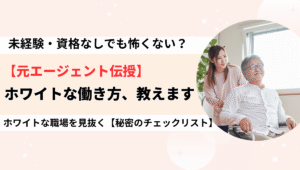
コメント